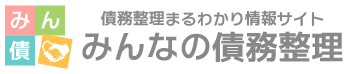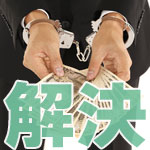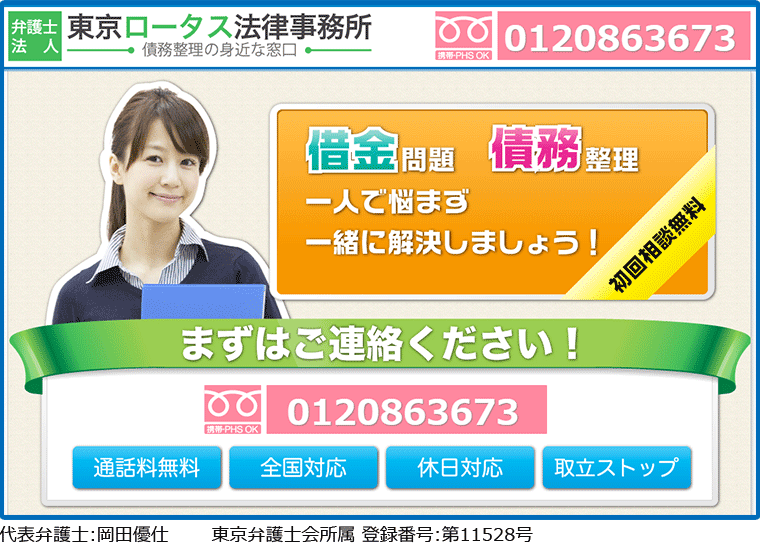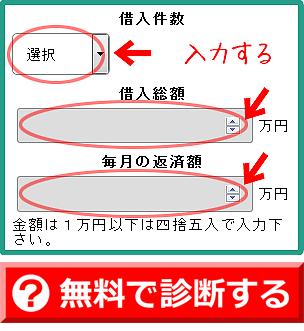債務整理を弁護士へ依頼したらどれくらいの期間で解決する?
債務整理を弁護士に依頼したら、一体どのくらいで期間で終わるのでしょうか?
自己破産にしろ任意整理にしろ、早く手続きを終わらせて免責になるか、和解して返済を始めたいところですよね。
債務整理にもいくつか種類があり、それぞれに特徴や手続きにかかる期間も変わってきます。また、自分が抱えている借金の状況によっても変わる場合があります。
自己破産、任意整理なら通常3~6ケ月ほど、民事再生なら7~8ヶ月、特定調停なら3~4ヶ月ほどで手続きが終わります。
あくまでも目安なので、借金の状況により手続きにかかる期間は変わります。
ここでは、債務整理の種類別にかかる期間を流れとともにご紹介します。
過払い金請求
かかる期間4ヶ月~8ヶ月(和解した場合)
※訴訟になるともっと長引くことも
大変度★★★☆☆
債権者にとって過払い金はなるべく払いたくないもの。よって長期化しやすい傾向にあり、また和解が成立しない場合は訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こしても第一審の判決に控訴をこしてくる会社もあり、お互いの妥協点が一致しないと長期戦を強いられることになるので大変さは★3つ。
過払い金返還請求の流れ
- 弁護士に過払い金請求を依頼
- 債権者に取引履歴の開示を請求
- 利息制限法による引き直し計算
- 債権者に過払い金請求
- 和解交渉
- 和解契約の締結または決裂なら訴訟へ
- 支払い開始
①弁護士に過払い金請求を依頼
まずは弁護士に過払い金請求の依頼をします。
②債権者に取引履歴の開示を請求
過去の取引履歴を債権者から弁護士または司法書士に送ってもらいます。
その際に受任通知も送付するため、このタイミングで取り立てや支払いが止まります。
※1~2週間
相談の際、事前に伝えておけば即日で取立をストップしてもらることも可能です。
③利息制限法による引直し計算
明細が送られてきたら、利息制限法による引き直し計算を行います。
※1~3ヶ月
※引き直し期間は債務状況による
引き直し計算とは、借り手側の立場から、利息制限法にもとづいて返済した場合の借金の残額を計算し直すことです。すでに利息制限法を超える利息を支払っていた場合は、その利息は元本に充てられたとみなすので、借金額が減ります。
2010年に貸金業法が改正されるまで、ほとんどの金業者は利息制限法ではなく出資法にもとづく金利で貸付してきたので、出資法に違反しないギリギリの9.2%のグレーゾーン金利で借りていた人は借金がかなり減ることや、過払い金が発生することもあります。
④債権者に過払い金請求
FAXや内容証明郵便で過払い金を請求します。
⑤債権者との和解交渉
電話などで債権者と交渉します。
⑥和解契約の締結
もし、和解が成立しなかった場合は訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こした際も、和解交渉は平行して行うのが一般的です。
和解した場合・訴訟した場合の比較
| 和解した場合 | 訴訟の場合 |
| 手続きが数ヶ月で済む | 手続きが半年以上かかることも |
| 弁護士費用20% | 弁護士費用25% |
| 回収率は70%~90% (50%を提示されることも) |
基本的に満額を回収することができる |
| 利息は回収不可 | 利息5%込みで請求可能 |
訴訟をした場合、満額が回収できますが、その分弁護士費用も高くついてしまうので、自分にはどちらが向いているのかよく考えてから訴訟をするか決めると良いでしょう。
各社の返済までの期間・回収率
和解か訴訟か考える際、こちらの各社ごとの回収率・期間も参考にしてみてください。
| 回収率 | 期間(和解の場合) | 期間(訴訟の場脚) | |
|---|---|---|---|
| アコム | 80%~100% | 4ヶ月~5ヶ月 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| プロミス | 80%~100% | 4ヶ月~6ヶ月 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| レイク | 80%~100% | 4ヶ月~5ヶ月 | 6ヶ月~7ヶ月 |
| CFJ | 60%~80% | 3ヶ月~4ヶ月 | 9ヶ月 |
| アイフル | 40%~50% | 6ヶ月~7ヶ月 | 1年 |
任意整理
手続きにかかる期間:2ヶ月~6ヶ月
返済期間:3~5年
大変度★☆☆☆☆
任意整理は、債務整理のなかで唯一裁判所を通さずにできるため、比較的早く終わります。
大体のことは弁護士・司法書士がやってくれるので、大変度も他に比べて1番少ない★ひとつ。
大まかな流れ
- 受任通知を送付
- 債権者に取引履歴の開示を請求
- 利息制限法による引き直し計算
- 和解交渉←ここがどれくらい長引くかが問題
- 和解契約の締結
- 支払い開始
①受任通知を送付
弁護士または司法書士に任意整理を依頼すると、
まず債権者に受任通知を送付します。
これにより、債権者からの取立が一旦ストップします。
受任通知とは、代理人が任意整理の手続きを行っていくことを通知するものです。
②債権者に取引履歴の開示を請求
受任通知を送付する際、取引当初からの取引履歴を債権者から弁護士または司法書士に送ってもらいます。
③利息制限法による引直し計算
明細が送られてきたら、利息制限法による引き直し計算を行います。
※ここまでで大体1~2カ月
④和解交渉
引き直し計算が終わり、返済できそうであれば、計算後の残額に基づいて債権者との和解交渉をはじめます。
一般的には残額を3年~5年の36回~60回回払いに分割し、将来の利息をカットします。(これからの返済は元本のみで利息を払わなくてよい)
しかしこれは業者によって異なります。返済期間をより短く設定してくる業者や、もっと長くしてくれる業者、利息カットができないケースもあります。
⑤和解契約の締結
和解契約が締結されると支払いが始まります。
⑥支払い開始
ここまでの①~⑤までの作業は弁護士または司法書士がやってくれます。あとは支払うだけです。
ここで決まった期限・返済額は滞りなく毎月返済していくことになります。
万が一返済が滞ると、期限の利益を喪失してしまいます。
期限の利益を喪失した場合、業者から残額を一括返済するよう請求されることになります。
最悪、その一括返済ができずに自己破産に陥ってしまうケースもあります。
そうならないためにも、和解契約書通りきちんと返済していきましょう!
個人再生
かかる期間:4ヶ月~半年前後(裁判所によって異なる)
大変度★★★★☆
個人再生には、個人再生委員が選出される裁判所と、されない裁判所があります。
個人再生委員が選出される裁判所の場合、さらに長く時間がかかります。
個人再生は手続きがかなり多く、再生債務者本人が行う手続きもあるので、債務整理の中でも大変な★4つ。
個人再生委員とは、債務者の財産や負債を調査して民事再生手続が妥当か判断し、手続きが適正に進むように監督する人です。
債権者と債務者の中立に立つ人で、裁判所によって選任されます。
個人再生委員が選出される場合とされない場合では手順もかかる日数も変わってきますので、今回は選出されない場合を大阪地裁、される場合を東京地裁の例で見ていきます。
大阪地裁の場合、再生計画の認可が決定するのにおおむね100日程度です。東京地裁の場合になるともっと長く、25週間くらいを要します。
個人再生委員が選出されない場合の流れ
大阪地方裁判所の例
- 弁護士・司法書士に相談・委任
- 受任通知の送付、取引履歴の開示請求、債権調査
- 個人再生の申立書の作成、申立
- 履行テスト開始
- 個人再生手続き開始
- 債権提出・債権調査
- 異議申述期間の開始
- 異議申述期間の期限
- 再生計画の作成・提出
- 書面決議実施の決定
- 書面決議の回答期限
- 再生計画の認可・不認可決定
- 認可決定確定
- 再生計画の遂行
①弁護士・司法書士に相談・委任
まずは弁護士・司法書士に相談して委任します。
②受任通知の送付、取引履歴の開示請求、債権調査
まず、受任通知を送付します。これにより、債権者からの取立が一旦ストップします。
その後は債権者に取引履歴の開示を請求し、それをもとに利息制限法による引き直し計算をして債権を調査します。
※ここまで1~2週間
③個人再生の申立書の作成、申立て
つぎに個人再生の申立書を作成します。申立書作成には膨大な書類が必要なため、ここで結構時間がかかります。
※ここまで1~2ヶ月
④履行テスト開始
弁済を続けられるかどうか、履行テストを行います。
テストでは、新しく預金口座を開設し、そこに1ヶ月あたりの計画弁済予定額と同じ額の予納金を毎月振り込むことで、判断します。
このテスト期間はだいたい6ヶ月。ここで積み立てたお金はその後返還されます。
⑤個人再生手続き開始
ここから個人再生の手続きが開始します。
※申立から2週間後
⑥債権提出・債権調査
申立から6週間後に債権届出提出期限を指定されます。その提出期限までに、債権者は裁判所に債権の届け出を送付します。
個人再生においては、債権者から送られてくる債権届出の管理は再生債務者が行います。ただし、弁護士が代理人になっている場合は代理人が行います。
⑦⑧異議申述
再生債権の金額について異議がある場合、一般異議申述期間に書面で異議を述べることができます。
※申立から8週間後
⑨再生計画の作成・提出
再生計画案には、借金の圧縮率と弁済方法と期間、共益債権や一般優先債権の支払い方法を記入します。そしてこの再生計画案は、再生債務者本人が自分で作成します。
申立から9週間目にこの提出期限が設けられますが、期限をすぎると手続きが廃止されてしまうので絶対に守りましょう。
共益債権や一般優先債権というのは、個人再生により減額されない債権。
共益費:離婚した配偶者の子どもへの養育費の支払いなど
一般優先債権:社会保険料や住民税などの税金
⑩書面決議実施の決定
再生計画案が提出されると、裁判所が、この案について各債権者が同意か不同意か書面にて通知する書面決議を行うかどうか決めます。
※⑧の意義申述から3日後までに行われます。
⑪債権者の回答
書面決議または意見聴取が決定したら、申立から14週間後までに書く債権者は再生計画案に意見書対するまたは回答書を提出して同意か不同意かを示します。
⑫再生計画の認可・不認可決定
そして申立から100日後(⑪債権者の回答から3日後)、裁判所が再生計画を認可とするか不認可とするか決定します。
⑬認可決定確定
さらに申立から130日後(⑫再生計画の認可・不認可決定から5週間後)にその決定が確定され、これでやっと手続きはおわりです。
⑭再生計画の遂行
ここからは毎月決められた弁済額を支払うだけです。返済遅延は再生計画を取り消しにしてしまう場合があるのでしっかり払っていきましょう。
個人再生委員が選出される場合の流れ
東京地方裁判所の例
- 弁護士・司法書士に相談・委任
- 受任通知の送付、取引履歴の開示請求、債権調査
- 個人再生の申立書の作成、申立て
- 個人再生委員の選任・面接
- 履行テスト開始
- 個人再生委員による意見書提出
- 個人再生手続き開始
- 債権提出・債権調査
- 債権認否一覧表・報告書提出
- 異議申述
- 評価申立
- 再生計画の作成・提出
- 書面決議実施の決定
- 債権者の回答
- 個人再生委員による意見書提出
- 再生計画の認可・不認可決定
- 認可決定確定
- 再生計画の遂行
①弁護士・司法書士に相談・委任
まずは弁護士・司法書士に相談して委任します。
②受任通知の送付、取引履歴の開示請求、債権調査
まず、受任通知を送付します。これにより、債権者からの取立が一旦ストップします。それから、債権者に取引履歴の開示を請求します。それをもとに利息制限法による引き直し計算をして債権を調査します。
※ここまで1~2週間
③個人再生の申立書の作成、申立て
つぎに個人再生の申立書を作成します。申立書作成には膨大な書類が必要なため、ここで結構時間がかかります。
※ここまで1~2ヶ月
④個人再生委員の選任・面談
申立てをすると、その日の内に個人再生委員が選任されます。そしてその1週間以内に個人再生委員と面談をして、申立書の内容について確認をとったり、再生手続きが妥当か判断するための聴取が行われます。
また、個人再生委員の選任に15万円程度の費用が必要になります。(⑤の履行テストで積立たお金がこの費用に充てられます。)
※申立から1週間以内
⑤履行テスト開始
再生計画認可決定後に弁済を続けられるかどうかをテストするために行います。新しく預金口座を開設し、そこに1ヶ月あたりの計画弁済予定額と同じ額の予納金を毎月振り込むことで、判断します。このテスト期間はだいたい6ヶ月。
⑥個人再生委員による意見書提出
個人再生委員との面談、第1回の予納金の振り込み後、申立から3週間以内に個人再生委員が手続きを開始すべきか判断し、裁判所に意見書を提出します。
⑦個人再生手続き開始
個人再生委員が提出した意見書をもとに裁判所が手続き開始に相当すると判断すると、申立からだいたい4週間後に個人再生手続き開始が決定します。
⑧債権提出・債権調査
申立から8週間後に債権届出提出期限を指定されるので、その指定期限までの間に、債権者は裁判所に債権の届け出を送付します。
個人再生においては、債権者から送られてくる債権届出の管理は、債務者自身が行います。
ただし、弁護士が代理人になっている場合は代理人が行ってくれます。
⑨債権認否一覧表・報告書提出
債権認否一覧表とは、債権者から送付された債権届け出に記載されている金額をもとに、その再生債権の金額を認めるか否かを記載するものです。報告書には、申立時から財産状況に変化がないかなどを記載します。
これらの書類の提出期限が、申立から10週間程度で決まるので、提出期限までに裁判所に提出します。
⑩異議申述
再生債権の金額について異議がある場合、一般異議申述期間に書面で異議を述べることができます。この期間が申立から13週間です。
これに対し、異議を述べられた再生債権者は異議があれば裁判所に評価申立をします。
⑪評価申立
異議申述から3週間以内であれば、異議を述べられた再生債権者は裁判所に評価申立を行うことができます。
⑫再生計画の作成・提出
再生計画案には、借金の圧縮率と弁済方法と期間、共益債権や一般優先債権の支払い方法を記入します。そしてこの再生計画案は、再生債務者本人が自分で作成します。
申立から9週間目にこの提出期限が設けられますが、期限をすぎると手続きが廃止されてしまうので絶対に守りましょう。
共益債権や一般優先債権というのは、個人再生により減額されない債権。
共益費:離婚した配偶者の子どもへの養育費の支払いなど
一般優先債権:社会保険料や住民税などの税金
⑬書面決議実施の決定
再生計画案が提出されると、個人再生委員が、再生計画案について各債権者からの同意・不同意などを確認する書面決議・意見聴取に値するかどうかの意見書が提出されます。
それに基づいて裁判所が最終的な決定をし、次の書面決議に進めるかどうかが決まります。これが申立から20週間後までに行われます。
⑭債権者の回答
書面決議または意見聴取が決定したら、申立から22週間後までに書く債権者は再生計画案に対する意見書または回答書を提出して同意か不同意かを示します。
⑮個人再生委員による意見書提出
各債権者からの回答を踏まえて、申立から24週間後までに、個人再生委員が再生計画を認可するか不認可とするかの意見書を提出します。
⑯再生計画の認可・不認可決定
そして申立から25週間後、裁判所が再生計画を認可とするか不認可とするか決定します。
⑰認可決定確定
さらに申立から29週間後にその決定が確定され、これでやっと手続きはおわりです。
⑱再生計画の遂行
ここからは毎月決められた弁済額を支払うだけです。返済遅延は再生計画を取り消しにしてしまう場合があるのでしっかり払っていきましょう。
自己破産
かかる期間3ヶ月~1年以上
大変度★★★☆☆
自己破産には大きく分けて2つの種類があります。「同時廃止」と「管財事件」です。このどちらになるかによってかかる時間も費用も大きく変わってきます。
同時廃止だと期間も3ヶ月程度で、費用も3万円程度になります。
ですが「管財事件」になると、期間は1年以上に長引くこともありますし、費用も最低50万~と非常に高額になります。
以上のことを踏まえて大変度は★3つ。
同時廃止…調査しても債権者に配当するだけの財産を持っていない場合、こちらの手続きになります。
管財事件…財産を持っている場合(生活する上で最低限必要なものは除く)、免責不許可事由に該当する場合。しかし一部の裁判所では「少額管財事件」となることもあります。
少額管財事件…管財人がこの管財事件は短い期間で終わるだろうと判断した場合は通常の管財事件よりも早い2ヶ月~3ヶ月で手続きが完了し、費用も最低20万に抑えられます。
※ただし、代理人が申立することが条件になっていることが多く、自分で本人申立をすると「少額管財事件」になることはありません。
しかし管財事件になることはごくまれなケース。今回もこのページでは、同時廃止の場合の手順を紹介します。
同時廃止の大まかな流れ
- 相談
- 依頼
- 受任通知
- 取引履歴開示請求
- 地方裁判所に申立
- 地方裁判所に申立書の提出
- 破産の審尋
- 破産手続開始
- 同時廃止決定
- 官報に公告・各債権者に裁判所から破産の通知
- 破産の確定
- 免責の審尋
- 免責許可の決定
- 官報に公告
- 免責の確定・復権
①②弁護士に相談・依頼
まずは弁護士・司法書士に相談、依頼します。自己破産は1人でも手続きが可能ですが、管財事件の可能性や、また法定に出頭する際代理人として出てもらえることを考えると依頼した方がスムーズです。
即日~1週間以内
③受任通知
弁護士、または司法書士に任意整理を依頼するとまず、債権者に受任通知を送付します。これにより、債権者からの取立が一旦ストップします。
受任通知とは、代理人が任意整理の手続きを行っていくことを通知するものです。
依頼から2~3日後
④取引履歴開示請求
取引履歴の開示請求は、何社から借り入れしているかや、債権者の対応によって異なりますが、少なくとも1~3ヶ月ほどかかることを想定しておきましょう。
⑤地方裁判所に申立
地方裁判所で申立書をもらいます。裁判所の破産科でもらえます。申立人の住所地を管轄している地方裁判所に申請しますが、住民票上の住所と現住所が異なる場合は現住所を管轄する地方裁判所に申請します。
⑥地方裁判所に申立書を提出
申立書を作成する際、必要な書類がたくさんあるので作成には結構時間がかかります。提出して不備がなければ、破産の審尋の日を決めます。
⑦破産の審尋
破産の審尋はだいたい申立書の提出から1ヶ月後。東京地裁などでは即日で行われる場合もあります。
弁護士・司法書士に依頼している場合は、代理人として法定に出頭してもらうことが可能です。本人が出頭する場合は、この審尋は省略されることが多いです。
⑧⑨破産手続き開始・同時廃止決定
破産手続き開始と終了が同じなので、同時廃止といいます。同時廃止が決定すると、免責の審尋日が決まります。
この破産手続きが開始すると法律上、破産者という扱いになります。
⑩⑪官報に公告・各債権者に裁判所から通知・破産の確定
官報に公告されるとともに破産者に通知がいきます。ここで破産が確定します。
約1ヶ月後
⑫免責の審尋
免責の審尋を行います。弁護士・司法書士がいる場合は同伴・代理で出頭が可能です。最近では、新破産法によって行われない場合も多くあります。
1ヶ月後
⑬⑭⑮免責許可の決定・官報に公告・免責許可の確定・復権
免責の審尋の後、債権者から特に異議がなければ免責が決定します。債権者によりますが、だいたい1ヶ月ほどです。
官報の公告を経て、約1ヶ月後には免責が確定し、破産手続き中に制限されていた資格や転居などが可能になります。(復権)
債務整理は弁護士・司法書士に任せると安心
以上のように、債務整理の手続きは、比較的簡単なものから煩雑なものまで様々です。
自己破産や個人再生の手続きでは裁判所を通す必要がありますし、任意整理や過払い金請求も引き直し計算などの専門知識が必要になってきます。
ですが専門家に任せてしまえば、代理としてほとんどの手続きを行ってくれるので安心で確実です。。
また、弁護士・司法書士に手続きを依頼しことをた知らせる「受任通知」が発送されることで取立がストップするのも大きなメリット。悩んでいるなら、まずは相談から。相談は無料で行っている所もたくさんあります!ぜひ相談してみましょう。
実績豊富でおすすめ|債務整理に強い弁護士・司法書士を6つに厳選!
債務整理に掛かる期間とは
債務整理は、借入れが膨らみその返済が困難または不可能になった場合に債務の減免や免除を求めるというものです。債務整理は法律で認められているものですが、いくつかの種類があり代表的なのが任意整理、自己破産、個人再生の3つです。
任意整理は弁護士や司法書士に依頼して個別の債権者に対して債務の減免を求めるものです。一方で自己破産は裁判所に申し出てすべての債務の免除を求めることになります。自己破産は弁護士を雇ってすべて代理で行ってもらうケースと司法書士に依頼して必要書類だけを作成し本人が申請に行くケース、また自身がすべての書類を用意して行うケースがあります。自己破産は債務整理の最終手段といえるもので、同時に一定の資産を失うことになります。一方で個人再生は裁判所に再生計画案を提出しそれに沿って債務の返済を目指すものです。個人再生のメリットは住宅ローンを別扱いにでき認められれば資産を遺すことができることですが、弁護士や司法書士に支払う費用がもっとも高額です。
どの債務整理も手続きが完了するまでの期間はその時々の状況によって変わってきますが、任意整理の期間としては3ヶ月程度で決着し、3年を目安に合意した債務を支払うことになります。一方で自己破産は裁判所に認められる必要があり最短では3ヶ月程度の期間で行なえますが、資産があるなどの場合には破産管財人などを選定する必要があり6ヶ月から1年程度の期間が必要です。また個人再生では再生計画案の作成から裁判所に認められるまで1年程度は必要で、認められると合意した債務を3年を目安に返済することになります。